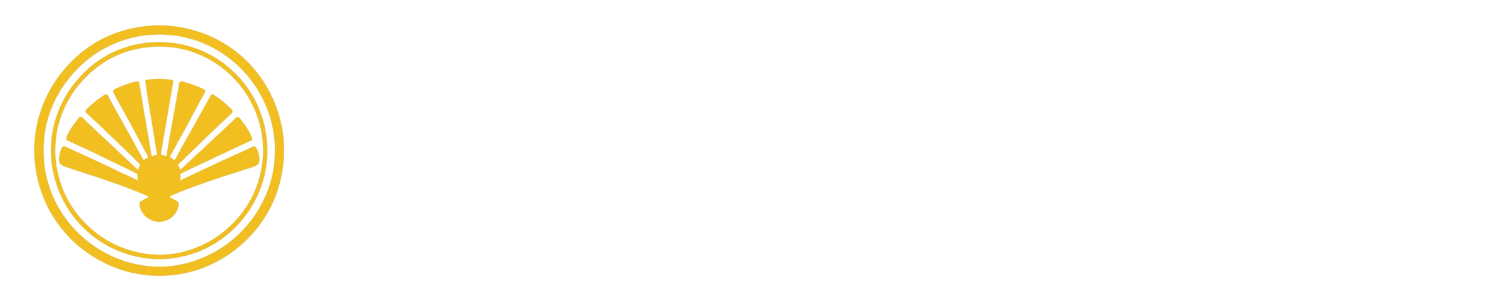戦争のニュースや、過去の出来事を目にしたとき、「なぜ、こんなことが起きたのだろう」と、そう思いながらも、どこかで距離を置いてしまう自分はいないでしょうか。残虐だった。冷酷だった。ひどい行為だった。そう言い切ってしまえば、少しだけ心は楽になります。
けれどそのたびに、私の中には、消えない問いが残るのです。その人は、どんな説明を受け、どんな時間を与えられ、どんな気持ちで、そこに立たされたのだろうか。誰かを裁く前に、その「入口」に、一度立ち止まってみたい。
今回は、戦争や残虐性の話を通して、人を変えてしまうのは何なのか、そして、人が人であり続けるために、私たちは何を守れるのか、そんなことを、皆様とご一緒に考えてみたいと思います。

戦争における残虐性や非人道的行為は、
しばしば「民族性」や「国民性」の問題として語られます。
「あの国の兵士は残虐だった」
「この民族は冷酷だ」
そうした言葉を耳にするたび、
私はいつも、胸の奥に小さな引っかかりを覚えます。
その人は、
どんな説明を受け、
どんな時間を与えられ、
どんな思いで、そこに立たされたのだろうか――
その問いが、消えずに残るのです。
本当に人を残虐にするものは、
血でも、民族でも、文化でもありません。
人を変えてしまうのは、
「どのような入口から、その場に立たされたのか」
その構造そのものではないか。
私は、そう思うのです。
▼ 覚悟を与えられた人間と、覚悟を奪われた人間
たとえば、同じ戦場に立つ二人の兵士がいるとします。
一人は、
自分の意思で、
何のために戦うのかを考える時間を与えられ、
恐怖や葛藤も含めて、覚悟を固めたうえで戦場に向かった人。
もう一人は、
突然連れ出され、
説明も納得もないまま、
銃を突きつけられ、命令だけを浴びせられて
無理やり戦場に放り込まれた人間。
この二人を、同じ「兵士」として語ることが、
本当にできるのでしょうか。
覚悟とは、勇ましさのことではありません。
それは、
「自分で引き受ける」という、人間としての尊厳です。
そしてその尊厳は、
本人だけのものではありません。
その人を信じ、支え、帰りを待つ人たちの人生とも、
深く結びついているものです。
その尊厳を守られたまま戦場に立つ人間と、
最初からそれを奪われた人間とでは、
行動が変わるのは、むしろ当然なのです。
▼ 残虐性は「性格」ではなく「環境」が生む
人は極限状態に置かれたとき、
必ず人間性を試されます。
しかし同時に、
その極限がどのように用意されたかによって、
人はまったく別の存在へと追い込まれてしまいます。
命令に逆らえば即処刑。
疑問を持つことは許されない。
自分の命も、仲間の命も、使い捨てにされる環境。
こうした入口から戦場に入った兵士は、
人であることを守る余地を、
少しずつ削り取られていきます。
それは本人の変化であると同時に、
その人と共に生きてきた家族や周囲の人々にとっても、
確実に影を落としていく変化です。
残虐行為は、
冷酷な性格の結果ではありません。
人間であることを保てない構造そのものが、
人間を残虐にしてしまうのです。
▼ 戦後の人生まで変えてしまう「入口」
この違いは、戦場だけで終わりません。
覚悟を持って戦場に立った人であっても、
戦後は深い苦しみを抱えて生きることになります。
しかしそこには、
「自分は何を背負ったのか」
「何をしてしまったのか」
を言葉にし、悔い、祈る余地が残されています。
その言葉は、
本人のためだけでなく、
ともに生き直そうとする人たちにとっても、
大切な橋渡しになります。
一方で、
覚悟を奪われたまま戦場に立たされた人は、
戦後もまた、別の地獄を生きることになります。
理由も意味も分からないまま行った行為。
否定すれば、自分自身が壊れてしまう記憶。
語る言葉を持てない沈黙。
その沈黙は、
本人の内側にとどまらず、
家庭や人間関係の中で、
長い時間をかけて広がっていくことすらあるのです。
▼ 問うべきは「誰が悪いか」ではない
だから私は、戦争を語るときに、
「どの民族が悪いか」
「どの国民性が劣っているか」
という問いを、できるだけ避けたいと思っています。
問うべきなのは、そこではありません。
問うべきなのは、
人間から覚悟を奪い、
人間であることを許さない入口を、
誰が、どのように作ったのか。
という構造です。
▼ 日本が持っていた、もう一つの「入口」
かつての日本では、
戦う意味を問い、
死を覚悟として引き受け、
戦場においても
「人としてどう在るか」を問い続ける。
そうした入口が、大切にされていました。
それは、
戦う者のためだけの思想ではなく、
見送る人、待つ人、支える人も含めて、
「どう生きるか」を共有するための入口だったのだと、
私は思います。
だからこそ日本人は、
戦争を美化するのではなく、
戦争そのものを恥じ、悼み、
二度と繰り返さぬと誓ってきたのではないでしょうか。
▼ 入口を変えれば、人は変わる
人は、生まれつき残虐なのではありません。
人は、最初から非人道的なのでもありません。
けれど、入口を誤れば、
誰でもそうなってしまう危うさを、
人間は持っています。
そしてその危うさは、
本人だけでなく、
その人と関わるすべての人の人生に、
影響を及ぼします。
逆に言えば、
入口が正しければ、
人はどこまでも人間であり続けることができる。
このことをもっとも深く理解していたのが、
武士でした。
武士道とは、
勇敢さの教えでも、
勝つための技術でもありません。
それは一貫して、
「どのような心で、事に臨むのか」
という入口を問い続ける思想だったのです。
▼ 新たな常識への挑戦
人が人であり続けられる社会とは、
「正しい答え」を配る社会ではありません。
正しい問いが、入口に置かれている社会です。
そして、その問いは、
家庭や学校、職場や地域といった、
日々の暮らしの中でこそ、
着実に育てられていくものだと、私は思っています。
一人ひとりが自立し、
自分の行動を自分で引き受け、
そのうえで、他者の尊厳や揺れに耳を澄ませる。
そうした姿勢が、
社会のあたりまえとして共有されていくこと。
それこそが、
互いに共震し、共鳴し、響き合える社会の土台になる。
正しい問いを、
戦場の入口に置くこと。
教育の入口に置くこと。
仕事や政治、日常の選択の入口に置くこと。
その積み重ねによって、
人は「命令に従う存在」ではなく、
「自ら考え、引き受け、響き合う存在」へと変わっていきます。
私は、
そうした社会常識の転換こそが、
静かに、しかし確実に、文明の向きを変えていく力になる
と、私は思っています。